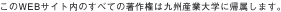科目名: 産業史セミナー
担当者: 加藤 要一
| 対象学年 | クラス | [001] | |
| 講義室 | 開講学期 | 後期 | |
| 曜日・時限 | 単位区分 | ||
| 授業形態 | 一般講義 | 単位数 |
| 準備事項 | |
| 備考 |
| 講義の目的・ねらい(講義概要) | 産業史研究の扱う範囲は、紡績、製鉄、機械工業等、西洋から移植された近代工業はもちろんのこと、在来産業である農業や伝統産業・地場産業まで広範囲である。この科目は、受講者自身が、これら日本の産業史にかんする研究テーマを設定し、図書館等における文献検索、一次資料の収集・整理、データ分析と考察にいたる「研究能力」の養成を第一目的とする。また同時に、産業史の関連文献の講読と討論により、基礎的知識や研究手法を習得し、また周辺諸分野の研究動向の把握をおこなって、自身の研究の深化をめざす。 |
| 講義内容・演習方法(講義企画) | "第1回 産業史研究の課題 産業史研究の対象と方法について講義。 第2回 調査研究法(1) 文献検索、資料収集の方法についての講義。 第3回 調査研究法(2) 戦前期の統計資料についての講義。 第4回 調査研究法(3) 戦後期の統計資料についての講義。 第5回 文献講読と討論(1) 農業関係文献の報告と討論。 第6回 文献講読と討論(2) 繊維産業関係文献の報告と討論。 第7回 文献講読と討論(3) 製鉄・機械産業関係文献の報告と討論。 第8回 文献講読と討論(4) 醸造業、商業関係文献の報告と討論。 第9回 研究報告と討論(1) 受講者の研究テーマの概略的報告。 第10回 研究報告と討論(2) 受講者の研究テーマについて、文献検索、資料収集の結果について報告と指導。 第11回 研究報告と討論(3) 受講者が収集した資料の整理法、解読法について報告と指導。 第12回 研究報告と討論(4) 受講者によるデータ入力と分析手法について報告と討論。 第13回 研究報告と討論(5) データ分析の結果報告と討論。 第14回 研究報告と討論(6) 受講者の最終的な研究報告と討論。 " |
| 評価方法・評価基準 | 受講者による主体的な研究活動を評価する。 |
| 履修の条件(受講上の注意) | 産業史研究、産業企業史研究、日本経済史研究、経営史研究のいずれかを受講し、基礎的な知識を習得していることが望ましい。 |
| 教科書 | 松田芳郎『データの理論』(東洋経済、1978年)、西川俊作・尾高煌之助・斎藤修編『日本経済の200年』(日本評論社、1996年) |
| 参考文献 | 古島敏雄『産業史Ⅲ』(山川出版社、1966年) |
| 特記事項(その他) |